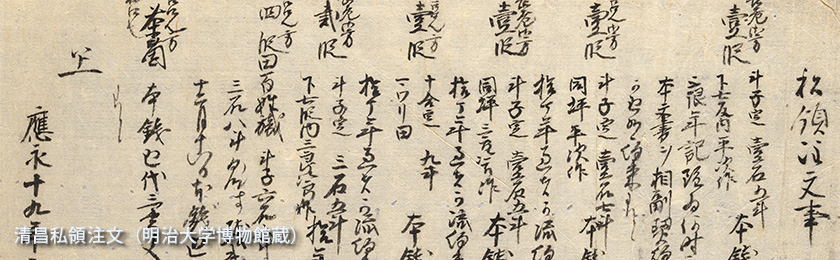大会・研究会
2025年度 第57回 学術大会のご案内
2025年8月9日更新
第57回大会の詳細が決定いたしましたので、ご案内申し上げます。公開講演と研究発表は非会員のご参加も可能です。非会員がご参加の場合、公開講演は無料、研究発表は500円を受付にて申し受けます。
■ 公開講演
■ 日時・会場
9月6日(土)P.M.1:00から(受付開始は正午)
北海道大学札幌キャンパス文系共同講義棟(軍艦講堂)6番教室
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西5丁目
北海道大学札幌キャンパス文系共同講義棟(軍艦講堂)6番教室
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西5丁目
■ 内容
足利義満と後小松天皇の関係について
河内 祥輔氏(北海道大学名誉教授)
幕末・近代を生きた、ある会津藩士の生涯
―北海道博物館特別展より―
―北海道博物館特別展より―
三浦 泰之氏(北海道博物館学芸部長)
■ 総会
■ 日時・会場
9月6日(土)P.M.4:30から
北海道大学札幌キャンパス文系共同講義棟(軍艦講堂)6番教室
北海道大学札幌キャンパス文系共同講義棟(軍艦講堂)6番教室
■ 懇親会
■ 日時・会場
9月6日(土)P.M.6:00から
カフェ de ごはん(北海道大学札幌キャンパス正門脇)
カフェ de ごはん(北海道大学札幌キャンパス正門脇)
■ 研究発表
■ 日時・会場
9月7日(日)A.M.9:30から(受付開始はA.M.9:00)
北海道大学札幌キャンパス文系共同講義棟(軍艦講堂)6番教室
北海道大学札幌キャンパス文系共同講義棟(軍艦講堂)6番教室
■ 内容
午前の部(A.M.9:30から)
1.「足利義満三万六千神祭記」考
野口 飛香留氏氏
2. 『暦林問答集』の清原良賢本系写本について
―慶應義塾大学所蔵文明写本と「大永三年」写本の紹介―
―慶應義塾大学所蔵文明写本と「大永三年」写本の紹介―
細井 浩志氏
3. 十五世紀前半における越後守護上杉氏の在京活動
―政治的・経済的活動を中心に―
―政治的・経済的活動を中心に―
佐藤 拓海氏
4. 連歌史料からみた室町時代の京都と南九州
―宗砌と宗砌流を中心に―
―宗砌と宗砌流を中心に―
川口 成人氏
5. 中世真如堂の経済基盤
井上 幸治氏
6. 戦国期大徳寺の寺領維持活動と人的交流
―大仙院の活動を中心に―
―大仙院の活動を中心に―
髙鳥 廉氏
午後の部(P.M.1:30から)
7. 禅僧と未来記・百王思想
―近江少林寺所蔵史料と新出『野馬台詩』―
―近江少林寺所蔵史料と新出『野馬台詩』―
芳澤 元氏
8. 天文年間における飛鳥井家の西国下向と南九州の地域権力
―鹿児島県歴史・美術センター黎明館所蔵「飛鳥井雅教蹴鞠免許状」の紹介をかねて―
―鹿児島県歴史・美術センター黎明館所蔵「飛鳥井雅教蹴鞠免許状」の紹介をかねて―
中村 昂希氏
9. 永禄年間後期における織田信長と武田信玄との関係
田中 秀幸氏
10. 『美濃国風土記』の再評価
塚本 明日香氏
11. 東大史料編纂所所蔵「金地院記録」から見る最岳元良と幕府の朝鮮外交
顧 明源氏
12.福山秘府』所載「大将軍足利義政公御教書」について
小澤 一平氏
※大会ポスターおよび会員にお送りした「大会案内」において、中村昂希氏のお名前の表記に誤りがありました。ご本人ならびに会員各位に謹んでお詫び申し上げ、ここに訂正させていただきます。
■ 文書見学会
■ 日時・会場
9月5日(金)P.M.2:00から(受付開始はP.M.1:30)
北海道博物館会議室(1階)
〒004-0006 北海道札幌市厚別区厚別町小野幌53-2
定員50名(事前申し込み・先着順)25名ずつの入れ替え制
終了予定P.M.5:00
北海道博物館会議室(1階)
〒004-0006 北海道札幌市厚別区厚別町小野幌53-2
定員50名(事前申し込み・先着順)25名ずつの入れ替え制
終了予定P.M.5:00
■ 内容
北海道博物館所蔵文書
(安斎家文書・水町家文書)
(安斎家文書・水町家文書)
■ その他
大会の会期中は北海道博物館にて特別展「新選組永倉新八と会津藩士栗田鉄馬―二人のサムライが歩んだ幕末・近代―」および総合展示を有料にてご覧いただけます(開館時間:A.M.9:30~P.M.5:00〔入館はP.M.4:30まで〕)
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会見学会(神奈川県立金沢文庫)のご案内
2023年11月13日更新
■ 集合日時
令和6年1月5日(金) 午後1時
■ 見学先
神奈川県立金沢文庫
〒236-0015 神奈川県横浜市金沢区金沢町142
〒236-0015 神奈川県横浜市金沢区金沢町142
■ 集合場所
金沢文庫ロビー(京浜急行 金沢文庫駅 徒歩15分)
■ 参加費
一般600円(団体20名以上の場合、団体割引500円)
■ 見学内容(詳細は以下のサイトにて)
神奈川県立金沢文庫 令和5年度特別展
中世寺院の書物 —聖教とそのかたち
中世寺院の書物 —聖教とそのかたち
■ その他
・事前申込みは不要です。
・展示室での担当学芸員等による解説を予定しておりますが、状況により、地下大会議室で解説をお聞きいただいたのち、各自展示をご観覧いただく可能性があります。
・展覧会閉幕間際であるため、混雑状況により一時的に人数制限を設ける場合がございます。
・見学会の翌6日を含む土曜、日曜には講座・講演会・シンポジウムがございます。詳しくは上記サイトにてご確認ください。こちらの聴講には事前申込みが必要です。
・展示室での担当学芸員等による解説を予定しておりますが、状況により、地下大会議室で解説をお聞きいただいたのち、各自展示をご観覧いただく可能性があります。
・展覧会閉幕間際であるため、混雑状況により一時的に人数制限を設ける場合がございます。
・見学会の翌6日を含む土曜、日曜には講座・講演会・シンポジウムがございます。詳しくは上記サイトにてご確認ください。こちらの聴講には事前申込みが必要です。
| ページの先頭に戻る |
2025年度 第57回 学術大会について
2025年3月31日更新
今年度の学術大会は、2025年9月5日(金)~7日(日)の日程で開催いたします。会誌98号の彙報では別の日程で開催を予定している旨をお知らせいたしましたが、諸般の事情により、9月5日~7日に変更・決定いたしました。5日は北海道博物館において史料見学会を、6日および7日は北海道大学札幌キャンパスにおいて公開講演と研究報告を実施いたします。詳細は8月初旬をめどに、本サイトおよび会員あて個別連絡にてお知らせいたします。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会見学会(京都府立京都学・歴彩館)のご報告
2025年3月31日更新
2024年度第2回の史料見学会を下記のとおり開催いたしました。
■ 開催日時
令和7年1月11日(土)午後1時~3時
■ 見学先
京都府立京都学・歴彩館
〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町1-29
〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町1-29
■ 見学内容
若杉家文書(陰陽道土御門家伝来文書)
| ページの先頭に戻る |
2024年度 第56回 学術大会のご案内
2024年7月25日更新
第56回大会の詳細が決定いたしましたので、ご案内申し上げます。公開講演と研究発表は非会員のご参加も可能です。非会員がご参加の場合、公開講演は無料、研究発表は500円を申し受けます。
■ 公開講演
■ 日時・会場
9月14日(土)P.M.1:00から(受付開始は正午)
國學院大學渋谷キャンパス2号館2104教室
〒150-8440 東京都渋谷区東4-10-28
國學院大學渋谷キャンパス2号館2104教室
〒150-8440 東京都渋谷区東4-10-28
■ 内容
『吉田家文書』と卜部氏・吉田神道
岡田 莊司氏(國學院大學名誉教授)
大御所秀忠時代の幕臣団と知行宛行状
根岸 茂夫氏(國學院大學名誉教授)
■ 総会
■ 日時・会場
9月14日(土)P.M.4:30から
國學院大學渋谷キャンパス2号館2104教室
國學院大學渋谷キャンパス2号館2104教室
■ 懇親会
■ 日時・会場
9月14日(土)P.M.6:00から
國學院大學渋谷キャンパス若木タワー18階 有栖川宮記念ホール
國學院大學渋谷キャンパス若木タワー18階 有栖川宮記念ホール
■ 研究発表
■ 日時・会場
9月15日(日)A.M.9:30から(受付開始はA.M.9:00)
國學院大學渋谷キャンパス2号館2104教室
國學院大學渋谷キャンパス2号館2104教室
■ 内容
午前の部 A.M.9:30から(受付開始はA.M.9:00)
1. 平安後期 石清水八幡宮寺宿院極楽寺の史的位置
比企 貴之氏
2. 南北朝期における幕府侍所と検非違使 ―「洛中警固」体制の形成過程を中心に―
水野 良紀氏
3. 勅問仰詞・申詞の様式、形状、使用形態とその系譜
小堀 貴史氏
4. 室町・戦国期の京都における酒とその流通 ―荘園との関係を中心に―
酒匂 由紀子氏
5. 伝本残存状況からみた大内家壁書
森谷 学氏
6. 改元定記の書写と利用 ―勘解由小路家(広橋家)における公事作法の継受―
中島 皓輝氏
午後の部(P.M.1:30から)
7. 戦国期の神階授与
桐田 貴史氏
8. 戦国期における室町幕府政所頭人伊勢氏の被官三上氏の基礎的考察
藤田 聡氏
9. 三木良頼の参議任官とその背景 ―(永禄六年)三月二三日付足利義輝御内書所載史料の検討を中心に―
大薮 海氏
10. 肥後宗像家と豊臣秀吉文書の伝来
花岡 興史氏
11. 大坂の陣研究と「戦功覚書」 ―井上与右衛門の戦功覚書を題材として―
堀 智博氏
12. 近世武家社会における「家」の「絶滅」観 ―香西頼山『七種宝納記』と松原基『続消暑漫筆』を素材として―
宇野 鈴音氏
■ 文書見学会
■ 日時・会場
9月16日(月)
A.M.9:50 國學院大學学術メディアセンター1階集合
A.M.10:00から 國學院大學図書館5階6会議室(正午頃解散)
A.M.9:50 國學院大學学術メディアセンター1階集合
A.M.10:00から 國學院大學図書館5階6会議室(正午頃解散)
■ 内容
國學院大學図書館所蔵文書
(久我家文書・吉田家文書・藤波家文書・森田清太郎旧蔵文書)
(久我家文書・吉田家文書・藤波家文書・森田清太郎旧蔵文書)
■ その他
大会の会期中は國學院大學博物館にて企画展「神輿―つながる人と人―」および常設展示をご覧いただけます(開館時間:A.M.10:00~P.M.6:00〔入館はP.M.5:30まで〕)
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会見学会(神奈川県立金沢文庫)のご案内
2023年11月13日更新
■ 集合日時
令和6年1月5日(金) 午後1時
■ 見学先
神奈川県立金沢文庫
〒236-0015 神奈川県横浜市金沢区金沢町142
〒236-0015 神奈川県横浜市金沢区金沢町142
■ 集合場所
金沢文庫ロビー(京浜急行 金沢文庫駅 徒歩15分)
■ 参加費
一般600円(団体20名以上の場合、団体割引500円)
■ 見学内容(詳細は以下のサイトにて)
神奈川県立金沢文庫 令和5年度特別展
中世寺院の書物 —聖教とそのかたち
中世寺院の書物 —聖教とそのかたち
■ その他
・事前申込みは不要です。
・展示室での担当学芸員等による解説を予定しておりますが、状況により、地下大会議室で解説をお聞きいただいたのち、各自展示をご観覧いただく可能性があります。
・展覧会閉幕間際であるため、混雑状況により一時的に人数制限を設ける場合がございます。
・見学会の翌6日を含む土曜、日曜には講座・講演会・シンポジウムがございます。詳しくは上記サイトにてご確認ください。こちらの聴講には事前申込みが必要です。
・展示室での担当学芸員等による解説を予定しておりますが、状況により、地下大会議室で解説をお聞きいただいたのち、各自展示をご観覧いただく可能性があります。
・展覧会閉幕間際であるため、混雑状況により一時的に人数制限を設ける場合がございます。
・見学会の翌6日を含む土曜、日曜には講座・講演会・シンポジウムがございます。詳しくは上記サイトにてご確認ください。こちらの聴講には事前申込みが必要です。
| ページの先頭に戻る |
2023年度 第55回 学術大会のご案内
2023年8月4日更新
本年度大会は、現時点では会場開催を予定しておりますが、台風接近などのため、一部または全部を中止、またはオンライン開催に切り替える可能性がございます。開催形態に変更が生じた場合には、本サイトおよび参加申込者個別宛にて、1週間前を目途にお知らせします。会場開催の方針が維持された場合には、特段のお知らせはいたしません。この変更にかかるキャンセル料などの責任は本会としては負いかねます。参加の如何は各自のご判断としてくださいます様、お願いします。その他詳細は、会員のみなさまへは大会案内を発送しておりますので、そちらをご確認ください。
■ 公開講演
■ 日時・会場
9月23日(土)P.M.1:00から
対馬市交流センター イベントホール
〒817-0021 長崎県対馬市厳原町今屋敷661番地
対馬市交流センター イベントホール
〒817-0021 長崎県対馬市厳原町今屋敷661番地
■ 内容
対馬の中世文書
佐伯 弘次氏(九州大学名誉教授)
十六世紀以前の朝鮮使節が見た対馬
村井 章介氏(東京大学名誉教授)
■ 総会
■ 日時・会場
9月23日(土)P.M.4:30から
対馬市交流センター イベントホール
対馬市交流センター イベントホール
■ 懇親会
■ 日時・会場
9月23日(土)P.M.6:00から
料亭 志まもと
〒817-0022 長崎県対馬市厳原町国分1380
料亭 志まもと
〒817-0022 長崎県対馬市厳原町国分1380
■ 研究発表
■ 日時・会場
9月24日(日)A.M.10:00から
対馬市厳原地区公民館大会議室(対馬市交流センター3階)
対馬市厳原地区公民館大会議室(対馬市交流センター3階)
■ 内容
午前の部(A.M.10:00から)
1. 鎌倉期における山門護持僧 ―出自・法流・修法活動に注目して―
袁 也氏
2. 中世の醍醐寺における教相伝授について ―教相「大事」の形成を通して―
姜 錫正氏
3. 鎌倉末~南北朝期の松殿家と信濃国小河荘
田中 勇作氏
4. 対馬小野家文書『(高麗陣)覚』について
米谷 均氏
午後の部(P.M.1:30から)
5. 十四世紀東寺の評定衆制度
貝塚 啓希氏
6. 九州における足利直冬軍事関係文書の研究 ―「馳参」と「於国致忠節」―
山本 隆一朗氏
7. 麹室料頭宛行状の機能と様式
村上 絢一氏
8. 対馬築城文書について
佐藤 凌成氏
9. 大友氏の筑前国支配と城督 ―天正期博多の事例を中心に―
村山 緑氏
■ 史料見学会
■ 日時・会場
9月25日(月)
午前の部(古文書見学会)A.M.9:30に対馬博物館入口集合(正午解散予定)
午前の部(古文書見学会)A.M.9:30に対馬博物館入口集合(正午解散予定)
■ 内容
午前の部
対馬博物館(平常展特集「対馬の古文書展」)
長崎県対馬歴史研究センター(『宗家文書』修復作業を見学)
対馬博物館(平常展特集「対馬の古文書展」)
長崎県対馬歴史研究センター(『宗家文書』修復作業を見学)
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会史料見学会の開催
2022年7月23日・24日実施
■ 開催日時
令和4年7月23日(土)・24日(日)
■ 見学先
成田山書道美術館
〒286-0023 千葉県成田市成田640
香取神宮神徳館
〒287-0017 千葉県香取市香取1697-1
〒286-0023 千葉県成田市成田640
香取神宮神徳館
〒287-0017 千葉県香取市香取1697-1
■ 集合場所
成田山書道美術館前集合
■ 参加費
1,000円
■ 日程
7月23日(土)
12時30分 成田山書道美術館
見学史料: 大慈恩寺文書、松崎コレクション(主に古代写経類)、成田山関係文書
18時~ 懇親会(ホテルウェルコ成田) 会費6,000円 要事前申し込み
12時30分 成田山書道美術館
見学史料: 大慈恩寺文書、松崎コレクション(主に古代写経類)、成田山関係文書
18時~ 懇親会(ホテルウェルコ成田) 会費6,000円 要事前申し込み
7月24日(日)
午前9時出発 集合場所 京成成田駅東口 コンフォートホテル前
大慈恩寺~堀籠~水郷佐原山車会館駐車場
(昼食休憩)
13時40分 香取文書見学会(解説:鈴木哲雄氏) 香取神宮神徳館 大会議室
16時香取神宮出発 JR佐原駅経由で京成成田駅東口まで向かいます。
午前9時出発 集合場所 京成成田駅東口 コンフォートホテル前
大慈恩寺~堀籠~水郷佐原山車会館駐車場
(昼食休憩)
13時40分 香取文書見学会(解説:鈴木哲雄氏) 香取神宮神徳館 大会議室
16時香取神宮出発 JR佐原駅経由で京成成田駅東口まで向かいます。
■ 定員
25名
| ページの先頭に戻る |
2022年度 第54回 学術大会のご案内
2022年7月14日更新
本年度大会は会場開催とすることと確定しました(9月2日更新)。会員を対象とした参加申込みは9月9日(金)にて締切りました。公開講演と研究発表は非会員の参加も可能です。非会員がご参加の場合、前者は無料、後者は500円を申し受けます。
■ 公開講演
■ 日時・会場
10月1日(土)P.M.1:00から
別府大学 32号館 400番教室
〒874-8501 大分県別府市北石垣82
別府大学 32号館 400番教室
〒874-8501 大分県別府市北石垣82
■ 内容
「鎌倉遺文データベースの課題発見的利用」拾遺
田村 憲美氏(別府大学名誉教授)
大分県の中世文書の特徴
飯沼 賢司氏(別府大学特任教授)
■ 総会
■ 日時・会場
10月1日(土)P.M.4:30から
別府大学
〒874-8501 大分県別府市北石垣82
別府大学
〒874-8501 大分県別府市北石垣82
■ 懇親会
※本年度は懇親会を中止とさせていただきます
■ 研究発表
■ 日時・会場
10月2日(日)A.M.10:00から
別府大学
〒874-8501 大分県別府市北石垣82
別府大学
〒874-8501 大分県別府市北石垣82
■ 内容
午前の部(A.M.10:00から)
1. 平安貴族社会の儀礼・政務と〈メディア〉 -仁王会立紙の「発見」-
黒羽 亮太氏
2. 大和国栄山寺領の歴史的景観 -GISによる平安中後期坪付の解析を中心に-
赤松 秀亮氏
3. 大宰大弐大内義隆の北部九州支配 -大府宣の分析を中心に-
藤立 紘輝氏
4. 豊前国宮時荘の変遷とその構造 -羅漢寺住持職をめぐる相論に着目して-
三谷 紘平氏
午後の部(P.M.1:30から)
5. 毛利氏の九州進出と北部九州の国衆の役割
佐藤 凌成氏
6. 戦国期公武交渉文書としての女房奉書 -発給過程と機能-
柴田 修平氏
7. 大友氏発給文書の原本調査による古文書学的分析
松尾 大輝氏
8. 島津氏領内にみる一向宗禁制政策とキリスト教禁制政策の内実と差違
濵島 実樹氏
■ 史料見学会
■ 日時・会場
10月3日(月)
午前の部(古文書見学会)A.M.10:00から 大分県立先哲史料館にて
午後の部(古文書見学会)P.M.1:00以降 国東半島の史跡を見学後、大分空港、別府駅にて解散(予定)
午前の部(古文書見学会)A.M.10:00から 大分県立先哲史料館にて
午後の部(古文書見学会)P.M.1:00以降 国東半島の史跡を見学後、大分空港、別府駅にて解散(予定)
■ 内容
午前の部
大分県立先哲史料館(高野山本覚院文書、渡辺文庫、都甲文書、余瀬文書、永弘文書)
大分県立先哲史料館(高野山本覚院文書、渡辺文庫、都甲文書、余瀬文書、永弘文書)
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会史料見学会の開催
2021年11月26日実施
■ 開催日時
令和3年11月26日(金)
■ 見学先
神奈川県立金沢文庫
〒236-0015 神奈川県横浜市金沢区金沢町142
〒236-0015 神奈川県横浜市金沢区金沢町142
■ 集合場所
金沢文庫ロビー
■ 見学内容
特別展「よみがえる中世のアーカイブズ ―いまふたたび出会う古文書たち―」を見学します。
■ 参加費
一般500円(団体20名以上の場合、団体割引400円)※事前申込不要
| ページの先頭に戻る |
2021年度 第53回 学術大会の更新情報
2021年8月6日更新
過日、お知らせしました第53回学術大会は、緊急事態宣言期間の延長を受けまして、9月10日(金)に予定されておりました文書見学会は中止、11日(土)の講演会、総会、12日(日)の研究発表会につきましては、会員による事前申込者限定のオンライン開催とさせていただきます。定員70名程度を超過する申込みがございました場合は、抽選にて参加を限定させていただく場合がございます。 本件に関するお申し込み者全員に、事務局よりメールによる返信を差しあげますので、参加の可否を含む詳細はそちらにてご確認ください。新規ご入会者への対処も可能な限りさせていただきます。
| ページの先頭に戻る |
2021年度 第53回 学術大会のご案内
2021年7月27日更新
本年度は会員に限定し、定員を70名程度(11・12日。10日の定員は別途指定します)に限定した完全事前申込制にて実施します。会員のみなさまへは8月上旬を目途にご案内を差し上げます。案内記載の要領にて、8月27日(金)までにお申し込みください。また、新規入会も歓迎します。
■ 文書見学会
東京都もしくは千葉県において緊急事態宣言が8月22日以降も継続した場合は中止とします。
■ 日時・会場
9月10日(金)
午前の部(古文書見学会)A.M.9:30から 千葉市立郷土博物館にて
午後の部(古文書見学会)P.M.1:30から 成田山書道美術館にて
午前の部(古文書見学会)A.M.9:30から 千葉市立郷土博物館にて
午後の部(古文書見学会)P.M.1:30から 成田山書道美術館にて
■ 内容
午前の部
千葉市立郷土博物館(原(はら)文書)
午後の部
成田山書道美術館(大慈恩寺文書、松崎コレクション、成田山の近世文書)
千葉市立郷土博物館(原(はら)文書)
午後の部
成田山書道美術館(大慈恩寺文書、松崎コレクション、成田山の近世文書)
■ 公開講演
緊急事態宣言が8月22日以降も継続した場合はオンライン開催とします。
■ 日時・会場
9月11日(土)P.M.1:00から
学校法人成田山教育財団 成田高等学校
〒286-0023 千葉県成田市成田27
学校法人成田山教育財団 成田高等学校
〒286-0023 千葉県成田市成田27
■ 内容
香取文書の伝来と保存
鈴木 哲雄氏(都留文科大学教授)
東国寺院の中世文書 ―大慈恩寺文書にみる村落・武士・寺院―
外山 信司氏(千葉市立郷土博物館総括主任研究員)
■ 総 会
緊急事態宣言が8月22日以降も継続した場合はオンライン開催とします。
■ 日時・会場
9月11日(土)P.M.4:30から
学校法人成田山教育財団 成田高等学校
〒286-0023 千葉県成田市成田27
学校法人成田山教育財団 成田高等学校
〒286-0023 千葉県成田市成田27
■ 懇親会
※新型コロナウイルス感染拡大状況に鑑みて、本年度は懇親会を中止とさせていただきます
■ 研究発表
緊急事態宣言が8月22日以降も継続した場合はオンライン開催とします
■ 日時・会場
9月12日(日)A.M.10:00から
学校法人成田山教育財団 成田高等学校
〒286-0023 千葉県成田市成田27
学校法人成田山教育財団 成田高等学校
〒286-0023 千葉県成田市成田27
■ 内容
午前の部(A.M.10:00から)
1.伊勢神宮膝下領荘園と在地寺院
永沼 菜未氏
2. 中世後期の地方禅院における仏事と運営―丹波天寧寺を中心に―
山口 啄実氏
3. 戦国期禅僧ネットワークの実態に関する基礎的考察
―「南豊大和尚遷化之際書簡集」の分析を通じて―
―「南豊大和尚遷化之際書簡集」の分析を通じて―
岩永 紘和氏
4. 石見亀井家文書の年不詳文書について
深田 富佐夫氏
午後の部(P.M.1:30から)
5. 紀州徳川家伝来文書からみた慶長の役講和交渉
吉永 光貴氏
6. 寛政改革期の文書政策と寺社奉行・奏者番
吉川 紗里矢氏
7. 伊能忠敬「家訓」の再検討
酒井 右二氏
| ページの先頭に戻る |
2021年度学術大会について
2021年4月14日更新
昨年度中止となりました成田高等学校(千葉県成田市)での大会を、2021年9月10日(金)~12日(日)(2021年9月11日~13日から変更となりました)の日程で実施する予定です。詳細は後日お知らせします。
また、新型コロナウイルスの感染状況により、オンライン開催に移行する可能性がございます。7月を目途に確定させる見込みですので、最新情報にご留意ください。
また、新型コロナウイルスの感染状況により、オンライン開催に移行する可能性がございます。7月を目途に確定させる見込みですので、最新情報にご留意ください。
| ページの先頭に戻る |
2020年度総会の結果について
2020年10月5日更新
本年度総会は郵送にて執り行わせていただきました。
所定の期間内に質問・異議などはございませんでしたので、全ての報告事項は原案通り承認となりました。よろしくお願いいたします。
次年度大会は、2021年9月11日~13日の日程にて、今年度中止となった成田にて実施される予定です。コロナがそれまでには収束していることを祈念致しております。
所定の期間内に質問・異議などはございませんでしたので、全ての報告事項は原案通り承認となりました。よろしくお願いいたします。
次年度大会は、2021年9月11日~13日の日程にて、今年度中止となった成田にて実施される予定です。コロナがそれまでには収束していることを祈念致しております。
| ページの先頭に戻る |
2020年度学術大会の中止について
2020年8月1日更新
昨今のコロナ感染症をめぐる状況の急激な悪化を受けまして、現地開催校から中止の申し入れがありました。急速な沈静化が見えない以上、やむを得ないことと思います。今年度の成田大会は正式に中止とさせていただきます。
なお今年度の総会による審議事項は全て郵送によって執り行いたいと思います。会員のみなさまには追って通知が発送されますのでそれをご覧ください。
また次年度の大会はあらためて成田にて行うべく調整中です。
なお今年度の総会による審議事項は全て郵送によって執り行いたいと思います。会員のみなさまには追って通知が発送されますのでそれをご覧ください。
また次年度の大会はあらためて成田にて行うべく調整中です。
| ページの先頭に戻る |
2020年度学術大会について
2020年7月14日更新
4月にご案内しましたように、本年度の学術大会は9月12日~14日の日程で千葉県成田高校での開催を予定しております。すでに講演者・報告者も決まり、その他ほとんどの準備は終えていて開催を待つばかりの状態になっています。
しかしながら昨今の新型コロナウイルス流行状況の悪化により、中止せざるを得ない可能性もでてきました。従いまして正式な大会案内やポスターの発送を、8月上旬まで遅らせることとします。大会開催の正式決定については、しばしお待ちください。
なお8月上旬の段階で開催を決定しましても、9月上旬の状況によっては直前の開催中止になることもあり得ます。あらかじめご承知おきください。
しかしながら昨今の新型コロナウイルス流行状況の悪化により、中止せざるを得ない可能性もでてきました。従いまして正式な大会案内やポスターの発送を、8月上旬まで遅らせることとします。大会開催の正式決定については、しばしお待ちください。
なお8月上旬の段階で開催を決定しましても、9月上旬の状況によっては直前の開催中止になることもあり得ます。あらかじめご承知おきください。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会史料見学会のご案内
2019年10月16日更新
■ 開催日時
令和元年11月3日(日)
午後1時30分~午後3時 (午後1時受付開始)
午後1時30分~午後3時 (午後1時受付開始)
■ 見学先
駒澤大学禅文化歴史博物館
〒154-8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1
〒154-8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1
■ 集合場所
駒澤大学禅文化歴史博物館 1階展示室入口
■ 参加費
無料
■ 見学史料
駒澤大学禅文化歴史博物館企画展「家康を支えた一門 松平家忠とその時代~『家忠日記』と本光寺~」は、徳川家康の一門・深溝松平家忠(1555~1600)が書き残した『家忠日記』(駒澤大学図書館所蔵)と、深溝松平氏の菩提寺・本光寺(愛知県幸田町・長崎県島原市)に伝来する関係資料などの文化財から、戦国武将の実像に迫る展覧会です。担当学芸員の解説を交えて見学します。
詳細については、同展ホームページをご覧下さい。
(PDFパンフレットはこちら)。
詳細については、同展ホームページをご覧下さい。
(PDFパンフレットはこちら)。
■ 参加人数
30名前後を予定
■ 申込み方法
電子メールにて、お名前・ご連絡先・ご所属を明記の上、下記宛先までお申し込み下さい。10月28日(月)必着です。尚、申込者多数の場合は、会員優先・先着順にて対応させていただきますので、ご了承ください。
■ 申し込み先
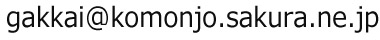
■ お問い合わせ先
〒154-8525東京都世田谷区駒沢1-23-1
駒澤大学文学部歴史学科 担当 林譲
yhayashi@komazawa-u.ac.jp ※@を半角にしてください
駒澤大学文学部歴史学科 担当 林譲
yhayashi@komazawa-u.ac.jp ※@を半角にしてください
| ページの先頭に戻る |
2019年度学術大会のご案内
2019年7月31日更新
■ 公開講演
■ 日時
9月14日(土)P.M.1:15から
出雲国の戦国争乱と中世文書
長谷川 博史氏(島根大学教育学部教授)
徳川政権による石見銀山支配と大久保長安
仲野 義文氏(石見銀山資料館館長)
出雲国の戦国争乱と中世文書
長谷川 博史氏(島根大学教育学部教授)
徳川政権による石見銀山支配と大久保長安
仲野 義文氏(石見銀山資料館館長)
■ 会場
島根県芸術文化センター「グラントワ」小ホール
〒698-0022 島根県益田市有明町5番15号
〒698-0022 島根県益田市有明町5番15号
■ 総 会
■ 日時
9月14日(土)P.M.4:30から
■ 会場
島根県芸術文化センター「グラントワ」小ホール
〒698-0022 島根県益田市有明町5番15号
〒698-0022 島根県益田市有明町5番15号
※総会終了後~懇親会までの間、「グラントワ」内県立石見美術館で開催中の特別展「益田氏VS吉見氏」を解説付きで観覧いただけます(要入場料)。
■ 懇親会
■ 日時
9月14日(土)P.M.6:00から
■ 会費
6,000円
■ 会場
レストラン・ポニィ(「グラントワ」正面エントランス付近)
〒698-0022 島根県益田市有明町5番15号
〒698-0022 島根県益田市有明町5番15号
■ 研究発表
■ 日時
9月15日(日)A.M.9:00から(午前の部)
■ 会場
「グラントワ」スタジオ1
■ 内容
午前の部(A.M.9:00から)
1. 『下毛野氏系図』及び『秦氏系図』の基礎的考察
西山 史朗氏
2. 鎌倉幕府の初期鎮西神社政策
渡邉 俊氏
3. 利休以前の茶について―鎌倉・南北朝期を中心に―
島崎 綾子氏
4. 筆跡研究試論―足利尊氏・直義自筆御内書を素材として―
宮崎 肇氏
5. 南北朝期における挙状の機能と効力について
真下 卓也氏
6. 南北朝期宗氏の対馬支配と少弐氏
松尾 大輝氏
7. 「饗料腰差酒肴」請取状の検討
村上 絢一氏
午後の部(P.M.1:00から)
8. 醍醐寺における法流相承と文書・聖教の生成―報恩院隆源を通して―
佐藤 亜莉華氏
9. 室町幕府における山城守護・侍所の管轄領域区分について
松井 直人氏
10. 室町幕府外様衆としての出雲尼子氏
西島 太郎氏
11. 戦国大名権力の港湾支配と地域社会―出雲・石見の事例から―
谷口 正樹氏
12. 戦国期石見国の在地領主温泉氏と石見銀山支配をめぐって
目次 謙一氏
13. 桜江山根家文書(島根県江津市個人蔵)の真継宗弘発給文書
倉恒 康一氏
14. 種子島家家臣団の研究
寺野 遼氏
15. 佐倉藩の牛痘種痘普及政策における藩医の役割
萱田 寛也氏
※会員以外の方のご来場も歓迎します。
※会員以外の方は、14日の公開講演会の入場は無料ですが、15日の研究発表会は受付で参加費500円をお納めください。
※会員以外の方は、14日の公開講演会の入場は無料ですが、15日の研究発表会は受付で参加費500円をお納めください。
※同日夜に、地元の石西の文化を学ぶれんげ草の会のご厚意により、再現された「中世の食」による懇親会を開催いたします。これについての詳細は、こちらを参照してください。
■ 文書見学会
■ 日時
9月16日(月・祝)
午前の部(古文書見学会)A.M.9:30から
(集合はA.M.9:20、「グラントワ」スタジオ1)
午前の部(古文書見学会)A.M.9:30から
(集合はA.M.9:20、「グラントワ」スタジオ1)
午後の部(現地見学会)P.M.1:0から
(集合はP.M.0:50、「グラントワ」ロータリー)
(集合はP.M.0:50、「グラントワ」ロータリー)
■ 参加費
午前の部 無料
午後の部 1,000円
午後の部 1,000円
■ 会場
午前の部 「グラントワ」スタジオ1
午後の部 現地見学会
午後の部 現地見学会
■ 内容
午前の部
島根県立古代出雲歴史博物館所蔵文書
・足利直冬下文(長門探題を攻略した高津氏に宛てられた文書)
・石見石田家文書(戦国時代の海運に関わった家の文書。毛利家関係)
・吉川元春判物(益田氏ら御神本一族ゆかりの伊甘郷に関する文書)
益田市所蔵または寄託文書
・安富家文書(南北朝時代の武家文書)
・梅津文書(中世の名主の家の文書)
・原馨氏所蔵増野家文書(益田氏と領内の神社との関係を示す文書。当時の貨幣についても興味深い資料あり)
ほか、追加の可能性あり。
・足利直冬下文(長門探題を攻略した高津氏に宛てられた文書)
・石見石田家文書(戦国時代の海運に関わった家の文書。毛利家関係)
・吉川元春判物(益田氏ら御神本一族ゆかりの伊甘郷に関する文書)
益田市所蔵または寄託文書
・安富家文書(南北朝時代の武家文書)
・梅津文書(中世の名主の家の文書)
・原馨氏所蔵増野家文書(益田氏と領内の神社との関係を示す文書。当時の貨幣についても興味深い資料あり)
ほか、追加の可能性あり。
午後の部
(貸切バスで廻ります)
七尾城跡・三宅御土居跡・萬福寺・染羽天石勝神社・医光寺・櫛代賀姫神社・ 福王寺・中須東原遺跡の見学。
七尾城跡・三宅御土居跡・萬福寺・染羽天石勝神社・医光寺・櫛代賀姫神社・ 福王寺・中須東原遺跡の見学。
※午後の部の定員は40名です。申し込み者数によっては、抽選によって事前に参加者を限定させていただくことがあります。
※午前の部は、原則として定員はありません。
※見学会は、1日目・2日目の参加の会員に限らせていただきます。郵便でお送りしました開会案内にしたがって、必ず事前にお申し込み下さい。
※午前の部は、原則として定員はありません。
※見学会は、1日目・2日目の参加の会員に限らせていただきます。郵便でお送りしました開会案内にしたがって、必ず事前にお申し込み下さい。
※この大会・見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会史料見学会のご案内
2019年1月17日更新
■ 開催日時
平成30年7月28日(土)
13時30分~15時 (13時受付開始)
13時30分~15時 (13時受付開始)
■ 見学先
神奈川県立金沢文庫展示室 (〒236-0015 横浜市金沢区金沢町142)
■ 集合場所
神奈川県立金沢文庫1階展示室入口
※各自、下記の参加費をお支払いの上お集まり下さい
※各自、下記の参加費をお支払いの上お集まり下さい
■ 参加費
20歳以上500円、20歳未満・学生400円、65歳以上100円(団体料金適用)
■ 見学内容
神奈川県立金沢文庫平成30年度特別展「安達一族と鎌倉幕府―御家人が語るもうひとつの鎌倉時代史―」は、鎌倉幕府との重要な転換点をなす安達泰盛とその時代を中心に、鎌倉幕府の動向と、鎌倉に根付いた真言密教のかかわりについて、ゆかりの文化財を通じて考える展覧会です。同展に出陳される国宝・重要文化財等を、会員の皆様向けに担当学芸員の解説を交えて見学します。詳細については、同文庫ホームページをご覧下さい。
■ 参加人数
30名前後を予定
■ 申込み方法
電子メールにて、お名前・ご連絡先・ご所属を明記の上、7月14日までに下記宛先までお申し込み下さい。申込者多数の場合は、会員優先・先着順にて対応させていただきます。
■ 申し込み先
〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1
法政大学文学部史学科小口研究室内 日本古文書学会事務局
法政大学文学部史学科小口研究室内 日本古文書学会事務局
事務局メールアドレス 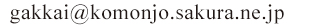
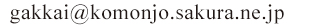
■ お問い合わせ先
〒113-0046 東京都文京区本郷7-3-1-1
東京大学史料編纂所(担当 林 譲)hayashi@hi.u-tokyo.ac.jp ※@を半角にしてください
東京大学史料編纂所(担当 林 譲)hayashi@hi.u-tokyo.ac.jp ※@を半角にしてください
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会史料見学会(東京大学史料編纂所)のご案内
2018年1月22日更新
■ 開催日時
平成30年3月15日(木)
15時~16時30分 (14時30分受付開始)
15時~16時30分 (14時30分受付開始)
■ 見学先
東京大学史料編纂所
■ 集合場所
東京大学史料編纂所 1階ロビー
■ 見学内容
東京大学文学部所蔵東大寺文書
・酒人内親王施入案 弘仁九年三月廿七日(1括1、『大日本古文書』別集一1号、以下同)
・東大寺封戸代米返抄 天喜四年五月二日(1括2-1、8号)
・某起請文 暦応三年十月晦日(1括2-14)
・東大寺封戸代米返抄 天喜四年八月六日(1括3-1、10号)
・僧頼仁田地直米請取状 久安五年二月 日(1括3-2、23号)
・源義用名田売券 貞和参年十一月廿六日(1括3-7、100号)
・印蔵文書出納日記(断簡六点) 承安五年~元暦元年(2括5-1~6、35号)
・河上荘犂谷田地手継券文案 (3括3、46号)
・僧貞玄起請文 正安元年六月廿五日(4括8、72号)
・長者宣等案文 (嘉元頃)五月廿六日(4括10、73号)
・東大寺別当実海御教書 正和五年五月七日(5括3、78号)
・周防与田保坪付案(前欠) 正和五年十月 日(5括4)
・大井荘下司職暦応五年算用状 暦応五年卯月 日(7括3、93号)
・室町将軍家御教書 明徳四年七月廿二日(9括3)
・大部荘領家方散用状 応永九年十一月 日(9括6)
・室町幕府過書 応永廿九年八月四日(9括11)
・蒲御厨東方年貢銭送状 康正三年十月八日(10括6)
・代官忠光等連署某所結解注進状(前欠) 明応二年卯月廿四日(11括3)
・友次起請文 永正四年十二月廿日(12括1)
・後伏見上皇院宣 (正和五年)十二月四日(13括1、84号)
・笠置寺一和尚覚舜請文 (鎌倉末)五月廿二日(13括2、88号)
・僧勝芸書状 十一月廿三日(13括4、43号)
・某書状(番外1)
・特別出陳(予定) 入船納帳(断簡三紙)
■ 参加人数
30名前後を予定
■ 申込み方法
電子メールにて、お名前・ご連絡先・ご所属を明記の上、3月5日までに下記宛先までお申し込み下さい。申込者多数の場合は、会員優先・先着順にて対応させていただきます。
■ 申し込み先
事務局メールアドレス 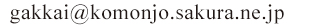
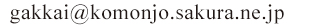
■ お問い合わせ先
〒113-0046 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学史料編纂所(担当 林 譲)hayashi@hi.u-tokyo.ac.jp ※@を半角にしてください
東京大学史料編纂所(担当 林 譲)hayashi@hi.u-tokyo.ac.jp ※@を半角にしてください
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
2018年度学術大会のご案内
2018年3月6日更新
■ 公開講演
■ 日時
9月8日(土)P.M.1:00から
古文書との出会い ― 一歴史地理学者の幸運 ―
金田 章裕氏(京都府立京都学・歴彩館館長)
東寺百合文書整理の一齣 ―新しい中世古文書学を目ざして―
上島 有氏(摂南大学名誉教授)
古文書との出会い ― 一歴史地理学者の幸運 ―
金田 章裕氏(京都府立京都学・歴彩館館長)
東寺百合文書整理の一齣 ―新しい中世古文書学を目ざして―
上島 有氏(摂南大学名誉教授)
■ 会場
京都府立京都学・歴彩館大ホール
〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町1-29
〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町1-29
■ 総 会
■ 日時
9月8日(土)P.M.4:00から
■ 会場
京都府立京都学・歴彩館大ホール
〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町1-29
〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町1-29
■ 懇親会
■ 日時
9月8日(土)P.M.6:00から
■ 会費
6,000円
■ 会場
デリカフェたまご京都北山(京都府立大学稲盛記念会館一階)
〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町1-5
〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町1-5
■ 研究発表
京都府立京都学・歴彩館大ホール
9月9日(日)A.M.9:30から(午前の部)
9月9日(日)A.M.9:30から(午前の部)
1. 正倉院文書にみえる女官の宣者についての考察
岡島 陽子氏
2. .古代文字のディジタル化とその活用の可能性
前田 亮氏・バトジャルガル ビルゲサイハン氏・李 康穎氏
3. 中条本『桓武平氏諸流系図』所収の両総平氏系図について
―成立時期と神代本『千葉系図』との比較を中心として―
―成立時期と神代本『千葉系図』との比較を中心として―
岩橋 直樹氏
4. 中世越前国滝谷寺をめぐる寺院ネットワーク
黄 霄龍氏
5. 東寺百合文書と杉原紙
富田 正弘氏
P.M.1:20から(午後の部) ※P.M.2:50~P.M.3:00は休憩
6. 足利義満をめぐる神祇祈禱の再検討
―天理図書館所蔵「凶徒御退治御告文」の分析を中心に―
―天理図書館所蔵「凶徒御退治御告文」の分析を中心に―
桐田 貴史氏
7. 中世東寺の「奉行合点状」と「多分」―器量と﨟次の視座から―
神子 美涼氏
8. 陽明文庫の漢籍
芳村 弘道氏
9. 豊臣政権下における長岡藤孝の動向
谷橋 啓太氏
10. 老中招請に関する一考察 ―岡山藩池田家の事例を中心に―
池ノ谷 匡祐氏
※会員以外の方のご来場も歓迎します。
※会員以外の方は、8日の公開講演会の入場は無料ですが、9日の研究発表会は受付で参加費500円をお納めください。
※会員以外の方は、8日の公開講演会の入場は無料ですが、9日の研究発表会は受付で参加費500円をお納めください。
■ 文書見学会
■ 日時
9月10日(月)A.M.10:00から
■ 参加費
無料
■ 会場
京都府立京都学・歴彩館小ホール内
見学の内容
見学の内容
国宝・東寺百合文書ほかの見学
・寛治七年(一〇九三)七月二十日 明法博士惟宗国任勘文案 ほ函二
・建武五年(一三三八)三月十八日 勅使四条隆蔭奉仏舎利奉請状 こ函六十四
・貞治元年(一三六二)十月日 御々女重申状 し函三十四
・享徳三年(一四五四)四月十四日 室町幕府奉行人連署奉書 マ函八十八―一
・永禄八年(一五六五)七月日 三好義継禁制 せ函武八十四 他
・寛治七年(一〇九三)七月二十日 明法博士惟宗国任勘文案 ほ函二
・建武五年(一三三八)三月十八日 勅使四条隆蔭奉仏舎利奉請状 こ函六十四
・貞治元年(一三六二)十月日 御々女重申状 し函三十四
・享徳三年(一四五四)四月十四日 室町幕府奉行人連署奉書 マ函八十八―一
・永禄八年(一五六五)七月日 三好義継禁制 せ函武八十四 他
※定員は五十名です。申し込み者数によっては、抽選によって事前に参加者を限定させていただくことがあります。申込葉書に必ず確実に連絡が取れるメールアドレスをお書きください。
※見学会は、1日目・2日目の参加の会員に限らせていただきます。郵便でお送りしました開会案内にしたがって、必ず事前にお申し込み下さい。
※見学会は、1日目・2日目の参加の会員に限らせていただきます。郵便でお送りしました開会案内にしたがって、必ず事前にお申し込み下さい。
※この大会・見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会史料見学会
2018年3月6日更新
■ 開催日時
平成30年7月28日(土)
13時30分~15時 (13時受付開始)
13時30分~15時 (13時受付開始)
■ 見学先
神奈川県立金沢文庫展示室 (〒236-0015 横浜市金沢区金沢町142)
■ 集合場所
神奈川県立金沢文庫1階展示室入口
※各自、下記の参加費をお支払いの上お集まり下さい
※各自、下記の参加費をお支払いの上お集まり下さい
■ 参加費
20歳以上500円、20歳未満・学生400円、65歳以上100円(団体料金適用)
■ 見学内容
神奈川県立金沢文庫平成30年度特別展「安達一族と鎌倉幕府―御家人が語るもうひとつの鎌倉時代史―」は、鎌倉幕府との重要な転換点をなす安達泰盛とその時代を中心に、鎌倉幕府の動向と、鎌倉に根付いた真言密教のかかわりについて、ゆかりの文化財を通じて考える展覧会です。同展に出陳される国宝・重要文化財等を、会員の皆様向けに担当学芸員の解説を交えて見学します。詳細については、同文庫ホームページをご覧下さい。
■ 参加人数
30名前後を予定
■ 申込み方法
電子メールにて、お名前・ご連絡先・ご所属を明記の上、7月14日までに下記宛先までお申し込み下さい。申込者多数の場合は、会員優先・先着順にて対応させていただきます。
■ 申し込み先
〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1
法政大学文学部史学科小口研究室内 日本古文書学会事務局
法政大学文学部史学科小口研究室内 日本古文書学会事務局
事務局メールアドレス 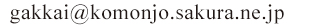
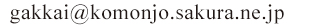
■ お問い合わせ先
〒113-0046 東京都文京区本郷7-3-1-1
東京大学史料編纂所(担当 林 譲)hayashi@hi.u-tokyo.ac.jp ※@を半角にしてください
東京大学史料編纂所(担当 林 譲)hayashi@hi.u-tokyo.ac.jp ※@を半角にしてください
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会史料見学会(東京大学史料編纂所)のご案内
2017年9月27日更新
■ 開催日時
平成30年3月15日(木)
15時~16時30分 (14時30分受付開始)
15時~16時30分 (14時30分受付開始)
■ 見学先
東京大学史料編纂所
■ 集合場所
東京大学史料編纂所 1階ロビー
■ 見学内容
東京大学文学部所蔵東大寺文書
・酒人内親王施入案 弘仁九年三月廿七日(1括1、『大日本古文書』別集一1号、以下同)
・東大寺封戸代米返抄 天喜四年五月二日(1括2-1、8号)
・某起請文 暦応三年十月晦日(1括2-14)
・東大寺封戸代米返抄 天喜四年八月六日(1括3-1、10号)
・僧頼仁田地直米請取状 久安五年二月 日(1括3-2、23号)
・源義用名田売券 貞和参年十一月廿六日(1括3-7、100号)
・印蔵文書出納日記(断簡六点) 承安五年~元暦元年(2括5-1~6、35号)
・河上荘犂谷田地手継券文案 (3括3、46号)
・僧貞玄起請文 正安元年六月廿五日(4括8、72号)
・長者宣等案文 (嘉元頃)五月廿六日(4括10、73号)
・東大寺別当実海御教書 正和五年五月七日(5括3、78号)
・周防与田保坪付案(前欠) 正和五年十月 日(5括4)
・大井荘下司職暦応五年算用状 暦応五年卯月 日(7括3、93号)
・室町将軍家御教書 明徳四年七月廿二日(9括3)
・大部荘領家方散用状 応永九年十一月 日(9括6)
・室町幕府過書 応永廿九年八月四日(9括11)
・蒲御厨東方年貢銭送状 康正三年十月八日(10括6)
・代官忠光等連署某所結解注進状(前欠) 明応二年卯月廿四日(11括3)
・友次起請文 永正四年十二月廿日(12括1)
・後伏見上皇院宣 (正和五年)十二月四日(13括1、84号)
・笠置寺一和尚覚舜請文 (鎌倉末)五月廿二日(13括2、88号)
・僧勝芸書状 十一月廿三日(13括4、43号)
・某書状(番外1)
・特別出陳(予定) 入船納帳(断簡三紙)
■ 参加人数
30名前後を予定
■ 申込み方法
電子メールにて、お名前・ご連絡先・ご所属を明記の上、3月5日までに下記宛先までお申し込み下さい。申込者多数の場合は、会員優先・先着順にて対応させていただきます。
■ 申し込み先
事務局メールアドレス 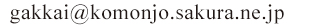
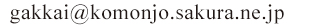
■ お問い合わせ先
〒113-0046 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学史料編纂所(担当 林 譲)hayashi@hi.u-tokyo.ac.jp ※@を半角にしてください
東京大学史料編纂所(担当 林 譲)hayashi@hi.u-tokyo.ac.jp ※@を半角にしてください
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
2017年度学術大会のご案内
2017年1月更新
■ 公開講演
■ 日時
10月14日(土)P.M.1:00から
琉球における国内発給文書の構成と機能 ―御朱印・言上写・印紙―
豊見山 和行氏(琉球大学法文学部教授)
歴代宝案と琉球家譜
田名 真之氏(沖縄県立博物館・美術館館長)
琉球における国内発給文書の構成と機能 ―御朱印・言上写・印紙―
豊見山 和行氏(琉球大学法文学部教授)
歴代宝案と琉球家譜
田名 真之氏(沖縄県立博物館・美術館館長)
■ 会場
沖縄県立芸術大学首里当蔵キャンパス一般教育棟三階大講義室
〒903-8602 沖縄県那覇市首里当蔵町114
〒903-8602 沖縄県那覇市首里当蔵町114
■ 総 会
■ 日時
10月14日(土)P.M.4:00から
■ 会場
沖縄県立芸術大学首里当蔵キャンパス一般教育棟三階大講義室
〒903-8602 沖縄県那覇市首里当蔵町114
〒903-8602 沖縄県那覇市首里当蔵町114
■ 懇親会
■ 日時
10月14日(土)P.M.6:00から
■ 会費
6,000円
■ 会場
ホテルサン沖縄
■ 研究発表
沖縄県立芸術大学首里当蔵キャンパス一般教育棟三階大講義室
10月15日(日)A.M.9:30から(午前の部)
10月15日(日)A.M.9:30から(午前の部)
1. 白河・鳥羽院政期における内裏修造事業
越川 真人氏
2. 戦国期における幕府奉行人家の分裂と再編
佐藤 稜介氏
3. キリシタン史研究における欧文古文書
森脇 優紀氏
4. 種子島の家譜史料とその周辺 ―種子島家の「歴史」と家臣が記した「歴史」―
屋良 健一郎氏
5. 唐代公文書体系試論
小島 浩之氏
P.M.1:00から(午後の部)
6. アジア世界における安南文書の様式について
藤田 励夫氏
7. 島津家文書に見える琉球国王・摂政・三司官発給文書料紙について
富田 正弘氏
8. 琉球国における芭蕉紙の品質とその利用 ―伝存史料の原本調査結果を中心に―
地主 智彦氏
9. ペリーがやってきた! ―事前に記されていた未来日記―
下郡 剛氏
10. 近世琉球における「御禁止之字」の研究 ―その諸相と歴史的意義に関する考察―
比嘉 吉志氏
11. 生子証文の基礎的研究
伊集 守道氏
12. 一九世紀における清琉間の外交戦術 ―尚家文書「道光一八年評価方日記」を中心に―
前田 舟子氏
※会員以外の方のご来場も歓迎します。
※会員以外の方は、14日の公開講演会の入場は無料ですが、15日の研究発表会は受付で参加費500円をお納めください。
※会員以外の方は、14日の公開講演会の入場は無料ですが、15日の研究発表会は受付で参加費500円をお納めください。
■ 文書見学会
■ 日時
10月16日(月)A.M.10:00から
■ 参加費
300円
■ 会場
那覇市歴史博物館
見学の内容
見学の内容
琉球国王尚家関係資料(「冠船日記」・「古案写」・「火花方日記」ほか)
沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館
見学の内容
見学の内容
鎌倉芳太郎資料(「図帳 当方」・「さはや御嶽[見取図及び平面図]」ほか)
※見学会は、1日目・2日目の参加の会員に限らせていただきます。郵便でお送りしました開会案内にしたがって、必ず事前にお申し込み下さい。
※この大会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会見学会(京都市歴史資料館)
2017年1月更新
■ 開催日時
平成29年9月9日(土)、16日(土)
14時~16時 (13時45分受付開始)
14時~16時 (13時45分受付開始)
■ 見学先
京都市歴史資料館(上京区寺町通荒神口下る)
■ 集合場所
京都市歴史資料館入り口
■ 見学内容
テーマ展「燈心文庫にみる室町時代の諸相」を見学します。『兵庫北関入船納帳』等、林屋辰三郎氏蒐集の室町後期を中心とする貴重な史料が展示されます。
■ 参加費
500円
定員の関係で2回に分けます。展示は同一内容です。参加希望の日(第一・第二希望)をご記入下さい。お申込み人数によっては調整させていただきます。 参加希望の方は、名前、所属、参加希望日、連絡先(メールアドレス、日程を第二希望に変更させていただいた場合のみ2,3日中に連絡します)を御記入の上、下記まで必ずハガキでお申し込み下さい。8月31日必着でお願い致します。
【宛先】 〒606-8501京都市左京区吉田二本松町
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会見学会(東京大学史料編纂所)
2016年6月更新
■ 開催日時
2016年11月10日(木) 午後3時(午後2時30分受付開始)~1時間
■ 集合場所
東京大学史料編纂所1階ロビーにて受付
■ 開催場所
2階演習室
■ 見学史料
■ 参 加 費
500円(展示図録代)
■ 参加人数
30名前後を予定
■ 募集方法
■ 問い合わせ先
東京大学史料編纂所(〒113-0046 東京都文京区本郷7-3-1)
担当 林譲
(eメール:hayashi@hi.u-tokyo.ac.jp)
※@は半角に変更してください
担当 林譲
(eメール:hayashi@hi.u-tokyo.ac.jp)
※@は半角に変更してください
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
2016年度 学術大会
2016年4月更新
■ 公開講演
■ 日時
9月24日(土)P.M.1:00から
中世文書から荘園景観を見る
海老澤 衷氏 (早稲田大学文学学術院教授)
古文書学研究の現状と課題
柴辻 俊六氏(前日本大学大学院講師)
■ 会場
早稲田大学国際会議場(井深大記念ホール)
〒169-0051 新宿区西早稲田1丁目20-14
〒169-0051 新宿区西早稲田1丁目20-14
■ 総会
■ 日時
9月24日(土)P.M.4:00から
■ 会場
早稲田大学国際会議場(井深大記念ホール)
〒169-0051 新宿区西早稲田1丁目20-14
〒169-0051 新宿区西早稲田1丁目20-14
■ 懇親会
■ 日時
9月24日(土)P.M.6:00から
■ 会費
6,000円
■ 会場
大隈ガーデンハウス三階
■ 研究発表
新宿区 早稲田大学国際会議場(井深大記念ホール)
9月25日(日)A.M.10:00から(午前の部)
9月25日(日)A.M.10:00から(午前の部)
1. 「雑様手実帳」の再検討-様工の請負的性格に関連して-
三野 拓也氏
2. 白河集古苑所蔵白河結城家文書「安達氏系図」の記載内容について
鈴木 由美氏
3.軍勢催促状の発給に関する一考察 -元弘~建武年間における軍事編成-
永山 愛氏
4.二通の「南禅寺慈聖院領諸庄園重書目録」
白川 宗源氏
P.M.2:00から(午後の部)
5. 室町~戦国期における伊勢氏の活動と発給文書
川口 成人氏
6. 中世後期日光山の山内支配と周辺勢力との関係-『日光山往古年中行事帳』を素材に-
小池 勝也氏
7. 戦国大名の在地掌握に関する一考察 -戦国期島津氏を題材として-
久下沼 譲氏
8. 豊臣政権の奉行発給・受給文書に関する一考察
中野 等氏
9. 幕藩領主と大坂落人 -細川忠興と後藤又市の関係を題材として-
堀 智博氏
※会員以外の方のご来場も歓迎します。
※会員以外の方は、24日の公開講演会の入場は無料ですが、25日の研究発表会は受付で参加費500円をお納めください。
※会員以外の方は、24日の公開講演会の入場は無料ですが、25日の研究発表会は受付で参加費500円をお納めください。
※この大会は終了しました。
| 過去の更新情報一覧に戻る |
■ 文書見学会
■ 日時
9月26日(月)A.M.9:30から(集合場所:早稲田大学中央図書館エントランス)
■ 参加費
無料
■ 会場
早稲田大学中央図書館
「近年の研究にみる早稲田大学所蔵史料」の見学
見学の内容
「近年の研究にみる早稲田大学所蔵史料」の見学
見学の内容
(1) 古代日本の国政と仏教を見る(「東大寺薬師院文書」など)
(1) 古代日本の国政と仏教を見る(「東大寺薬師院文書」など)
(2) 早稲田大学とイェール大学に残る俊乗房重源の継目裏花押文書
(3) 科研による共同研究のフィールド・東大寺領美濃国大井莊の検注帳
(4) 失われた常陸国吉田神社文書の復原
(5) 中世対外関係史研究の進展(「友山士偲度牒」など)
(6) 中世後期公武関係史論(「中原康雄私記」・「宣教卿記」など)
(7)「称名寺聖教・金沢文庫文書」の国宝指定に関連して
(1) 古代日本の国政と仏教を見る(「東大寺薬師院文書」など)
(2) 早稲田大学とイェール大学に残る俊乗房重源の継目裏花押文書
(3) 科研による共同研究のフィールド・東大寺領美濃国大井莊の検注帳
(4) 失われた常陸国吉田神社文書の復原
(5) 中世対外関係史研究の進展(「友山士偲度牒」など)
(6) 中世後期公武関係史論(「中原康雄私記」・「宣教卿記」など)
(7)「称名寺聖教・金沢文庫文書」の国宝指定に関連して
※大会期間中には、会場の井深大記念ホールに隣接する二階展示室にて、企画展「公家と武家の中世史」が開催中で、「後醍醐天皇綸旨」・「足利尊氏書状」など古文書約五十点が出陳されております。あわせてご観覧ください。
※見学会は、1日目・2日目の参加の会員に限らせていただきます。お送りしました開会案内にしたがって、必ず事前にお申し込み下さい。今回は当日受け付けることができませんのでご注意ください。
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会研究会(共催)のご案内
2015年10月更新
■ 概要
■ 日時
2016年3月4日 金曜日
9時30分~17時30分 (受付は9時から)
9時30分~17時30分 (受付は9時から)
■ 場所
東京大学史料編纂所福武ホール地下1F大会議室
■ 報告者とテーマ
報告1 遠藤基郎「科研の成果―東大寺文書関連データベースをさらに活用するために」
報告2 菊地大樹「中世東大寺堂家の活動について」
報告3 小原嘉記「鎌倉後期の東大寺大勧進とその周縁―禅律僧の登場」
―お昼休み-
報告4 畠山聡「東大寺図書館所蔵記録類の解題的研究」
報告5 西尾知己「東大寺衆中の室町期的展開」
―休憩―
討論 コメント:永村真・稲葉伸道・久野修義
■ 参加登録
下記のリンク先からお願い致します。
基盤研究(B)「復元的手法による東大寺文書研究の高度化―『東大寺文書目録』後の総括・展望―」グループ(代表遠藤基郎)・日本古文書学会共催

※この研究会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会見学会(敦賀市立博物館)
2015年7月更新
1. 開催日時
平成27年12月12日(土)
14時~16時 (13時45分受付開始)
14時~16時 (13時45分受付開始)
2. 見学先
敦賀市立博物館
3. 集合場所
敦賀市立博物館入り口
4. 見学内容
特別展「大谷吉継~人とことば」見学と市内の寺院文書を熟覧させていただきます。特別展で展示される原本は、多賀大社文書、真田家文書、大阪城天守閣所蔵文書、西福寺文書、小宮山家文書(敦賀の商人高嶋屋)など、パネル展示は島津家文書、吉川家文書、厚狭毛利家文書など、いずれも大谷吉継書状が中心。その他『慶長見聞書』(松平文庫、松平春嶽筆)、『慶長軍記』(京大附属図書館本、京大文学研究科図書館本)、『板坂卜斎覚書』(酒井家文庫、伴信友校訂本)等の軍記資料。
敦賀市内の寺院文書は、永建寺文書(鎌倉~戦国期の手継文書)、善妙寺文書(敦賀郡を中心とした寺領目録、敦賀郡司朝倉氏判物等)を拝見する予定です。
敦賀市内の寺院文書は、永建寺文書(鎌倉~戦国期の手継文書)、善妙寺文書(敦賀郡を中心とした寺領目録、敦賀郡司朝倉氏判物等)を拝見する予定です。
5. 参加費
500円+入場料(250円)
参加希望の方は、荒天などによる変更に備えて、連絡先を明記の上、下記までハガキにて御申し込みください。12月7日(月)必着でおねがいいたします。
【宛先】 〒606-8501京都市左京区吉田二本松町
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室

京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室

※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会見学会(大和文華館)
2015年3月更新
1. 開催日時
平成27年8月21日(金)
13時30分~15時30分 (13時15分受付開始)
13時30分~15時30分 (13時15分受付開始)
2. 見学先
大和文華館
3. 集合場所
大和文華館入り口前
4. 見学内容
大和文華館の特別企画展「中世の人と美術展」において、東京大学史料編纂所蔵の『中院一品記』等を拝見するとともに、大和文華館所蔵の双柏文庫から、中村直勝博士蒐集文書など、中世文書を熟覧させていただく予定です。
5. 参加費
500円+入場料(一般620円、学生・院生410円)
参加希望の方は、荒天などによる変更に備えて、連絡先を明記の上、下記までハガキにて御申し込みください。8月17日(月)必着でおねがいいたします。
【宛先】〒606-8501京都市左京区吉田二本松町
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
2015年度 日本古文書学会大会・総会
2015年3月更新
■ 公開講演
9月12日(土)P.M.1:00から
「備前国西大寺縁起絵巻と西大寺文書」中世文書からみた明応年間の復興造営
就実大学人文科学部教授 苅米 一志氏
縁起絵巻群の形成と保持
就実大学人文科学部教授 川崎 剛志氏
■会場 就実大学S館102号教室
〒703-8516 岡山県岡山市中区西川原1-6-1
■ 総会
9月12日(土)P.M.4:00から
■会場 就実大学S館102号教室
〒703-8516 岡山県岡山市中区西川原1-6-1
■ 懇親会
9月12日(土)P.M.6:00から
会費 6,000円(当日受付)
会費 6,000円(当日受付)
■会場 就実大学V館地下カフェテリア「ルボア」
■ 研究発表
岡山市 就実大学S館102号教室
9月13日(日)午前10時から(午前の部)
9月13日(日)午前10時から(午前の部)
1. 伊勢神宮庁宣の形態と機能
比企 貴之氏
2. 日蓮真筆文書の古筆学的考察
小林 正博氏
3. 中世東大寺の燈油関連組織 ―燈油目代・勧進所油倉・大仏殿燈油聖・大仏殿燈油納所―
遠藤 基郎氏
4. 中世的地域秩序の形成と再開発
朝比奈 新氏
P.M.1:00から(午後の部)
5. 割符の流通と信用―技術としての中世手形文書―
伊藤 啓介氏
6. 明応の政変後の室町幕府と寺社勢力
佐藤 稜介氏
7. 戦国期の御料所経営にみる都鄙関係 ―桐野河内村公文高屋氏を素材に―
吉永 隆記氏
8. 天正四年洛中勧進史料の作成過程に関する基礎的考察
長﨑 健吾氏
9. 豊臣政権の城番制
谷 徹也氏
10. 伊勢御師の為替利用―「来田文書」に見る清須黒田屋―
小林 郁氏
※会員以外の方のご来場も歓迎します。
※会員以外の方は、12日の公開講演会の入場は無料ですが、13日の研究発表会は受付で参加費500円をお納めください。
※会員以外の方は、12日の公開講演会の入場は無料ですが、13日の研究発表会は受付で参加費500円をお納めください。
※この大会は終了しました。
■ 文書見学会
9月11日(金) P.M.1:00から (集合場所:岡山県立博物館講堂)
参加費:750円。二日目の受付でお支払いください。
参加費:750円。二日目の受付でお支払いください。
■ 会場
岡山県立博物館(P.M.1:00~)・林原美術館(P.M.3:15~)
金山寺文書(「足利尊氏御教書」ほか)、石谷家文書などの見学
※見学会は、2日目・3日目参加の会員に限らせていただきます。
金山寺文書(「足利尊氏御教書」ほか)、石谷家文書などの見学
※見学会は、2日目・3日目参加の会員に限らせていただきます。
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会研究会(史料見学会)のご案内
2014年11月更新
■ 概要
■ 場所
京都市歴史資料館(市バス河原町丸太町下車徒歩5分、地下鉄丸太町駅下車 徒歩10分)
■ 日時
第1回目 2015年4月18日(土)
第2回目 2015年5月16日(土)
各回、何れも午後2時から2時間程度
(受付は午後1時45分から)
第2回目 2015年5月16日(土)
各回、何れも午後2時から2時間程度
(受付は午後1時45分から)
■ 集合場所
資料館玄関前
■ 参加費
500円程度
■ 見学要領
第1回目・第2回目とも
前半;於1F展示室、館員宇野日出生氏の解説により賀茂別雷神社巻子装文書を中心に見学
後半;於B1F研修室、展示以外の同巻子装文書を閲覧
前半;於1F展示室、館員宇野日出生氏の解説により賀茂別雷神社巻子装文書を中心に見学
後半;於B1F研修室、展示以外の同巻子装文書を閲覧
■ 募集人員と応募要領
募集人員は各回とも20名以内。往復葉書の往信裏面に⒧希望の回(①②回の間に展示替えがあります。両方希望の場合は希望順を記す)、⑵氏名・⑶住所(返信用葉書の表にも)、⑷所属を明記のうえ、下記の申し込み先を往信宛先として、3月31日(火)必着(ただしそれ以前でも、各回20名に達し次第締め切り)にて郵送ください。申し込み結果については、締め切り後、ただちに返信用葉書にてお知らせします。
なお、本企画に関する事前のお問い合わせは(参加申し込みは別)、t-sugi@lt.ritsumei.ac.jp 宛てに限り対応します。
なお、本企画に関する事前のお問い合わせは(参加申し込みは別)、t-sugi@lt.ritsumei.ac.jp 宛てに限り対応します。
【申し込み先】
〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
※この研究会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会研究会のご案内
2014年8月更新
■ 概要
■ 場所
京都府立総合資料館(地下鉄北山駅下車)
2階会議室
2階会議室
■ 日時
2015年1月24日 土曜日
14時~15時半頃 (受付は13時45分から)
14時~15時半頃 (受付は13時45分から)
■ 集合場所
資料館玄関前
■ 参加費
500円程度
■ 報告者とテーマ
(1)小森浩一氏(京都府立総合資料館)
「東寺百合文書のデジタル化について」
「東寺百合文書のデジタル化について」
(2)岡本隆明氏(京都府立総合資料館)
「『東寺百合文書WEB』のつかいかた」
「『東寺百合文書WEB』のつかいかた」
東寺百合文書のデジタル化に関するご講演と、WEBを用いたデモンストレーションが行われます。終了後、質疑応答も予定しております。ふるってご参加ください。
参加希望の方は、下記までハガキにてお申し込みください。1月19日(月)必着でおねがいいたします。
参加希望の方は、下記までハガキにてお申し込みください。1月19日(月)必着でおねがいいたします。
【申し込み先】
〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
※この研究会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会研究会
2014年5月更新
■ <研究会テーマ>
「中世・近世文書料紙研究の現状について」
参加費無料
参加費無料
■ 日時
2014年12月6日 土曜日
13時30分~17時 (受付は13時から)
13時30分~17時 (受付は13時から)
■ 場所
東京大学史料編纂所大会議室
(情報学環福武ホール地下1階)
(情報学環福武ホール地下1階)
■ <報告者と論題>
(1)高島晶彦氏(東京大学史料編纂所)
「デジタルを応用した古文書料紙の分析」
「デジタルを応用した古文書料紙の分析」
(2)本多俊彦氏(高岡法科大学)
「福井藩の知行宛行状について」
「福井藩の知行宛行状について」
(3)富田正弘氏(富山大学名誉教授)
「文書料紙の中世と近世-杉原紙と奉書紙-」
「文書料紙の中世と近世-杉原紙と奉書紙-」
参加ご希望の方は、郵便はがき又はeメールにて、お名前・ご連絡先・ご所属を明記の上、下記宛先までお申し込みください。
11月30日(日)必着でおねがいいたします。
11月30日(日)必着でおねがいいたします。
【申し込み先】
〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨3-20-1
大正大学文学部堀口研究室
eメール : komonjo@mail.tais.ac.jp
〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨3-20-1
大正大学文学部堀口研究室
eメール : komonjo@mail.tais.ac.jp
※この研究会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
2014年度 日本古文書学会大会・総会
2014年4月更新
■ 公開講演
9月27日(土)P.M.1:30から
平安朝「明法学」の展開と日本古典籍
皇學館大学学長 清水 潔氏
古文書学と木簡学
京都大学大学院文学研究科教授 吉川 真司氏
■会場 皇學館大学621教室
〒516-8555 三重県伊勢市神田久志本町1704
■ 総会
9月27日(土)P.M.4:00から
■会場 皇學館大学621教室
〒516-8555 三重県伊勢市神田久志本町1704
■ 懇親会
9月27日(土)P.M.6:00から
会費 6,000円(当日受付)
会費 6,000円(当日受付)
■会場 皇學館大学内 倉陵会館2階食堂
■ 研究発表
伊勢市 皇學館大学621教室
9月28日(日) A.M.9:00から(午前の部)
9月28日(日) A.M.9:00から(午前の部)
1、『法隆寺伽藍縁起并流記資財帳』にみえる「心経」
赤木 隆幸氏
2、頼朝死後の鎌倉幕府と北条氏
山本 みなみ氏
3、守護制度と使節遵行との関係の再検討
-南北朝期室町幕府の地域支配に関する一考察-
-南北朝期室町幕府の地域支配に関する一考察-
堀川 康史氏
4、図書寮本『日本書紀』巻第二の再検討
坂口 太郎氏
5、九州南朝の軍事指揮者に関する一考察-軍忠状証判者の検討を中心に-
山本 隆一朗氏
6、南北朝・室町期の都市鎌倉と東国武士
植田 真平氏
P.M.13:00から(午後の部)
7、中世後期北野社祠官組織と竹内門跡-祈祷命令文書の分析を中心として-
杉谷 理沙氏
8、蒙求臂鷹往来について-第九条(九月)往来を中心として-
山名 隆弘氏
9、中世京都における法華宗寺院の牛玉宝印
三 好 俊氏
10、戦国期大友氏の加判衆と「国衆」
窪田 頌氏
11、豊臣期における武家身分
井手 麻衣子氏
12、近世後期における江戸幕府奏者番の新役手留と系統
吉川 紗里矢氏
13、幕府役職への就任における職務情報の授受と「両敬」
-飯田藩主堀親寚・親義父子を事例に-
-飯田藩主堀親寚・親義父子を事例に-
千葉 拓真氏
14、近世後期の伊勢における芸能文化の受容
神谷 朋衣氏
※会員以外の方のご来場も歓迎します。
※会員以外の方は、1日目の公開講演会の入場は無料ですが、2日目の研究発表会は受付で参加費
500円をお納めください。
※会員以外の方は、1日目の公開講演会の入場は無料ですが、2日目の研究発表会は受付で参加費
500円をお納めください。
※この大会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会見学会(大阪城天守閣)
2013年11月更新
■ 日本古文書学会見学会のご案内
1. 場所
大阪城天守閣
2. 日時
4月20日 日曜日
15時~17時 (受付は14時45分から)
15時~17時 (受付は14時45分から)
3. 集合場所
天守閣改札前
4. 参加費
500円
大阪城天守閣にて春のテーマ展「乱世からの手紙―大阪城天守閣収蔵古文書選―」を見学いたします。大阪城天守閣の収蔵品から逸品を選りすぐり、古文書の魅力をわかりやすく伝える展覧会です。ふるってご参加ください。
なお、展覧会の会期は3月21日(金)~5月6日(火・振り替え休日)です。
参加希望の方は、下記までハガキにてお申し込みください。
4月15日(水)必着でおねがいいたします。
【申し込み先】〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
なお、展覧会の会期は3月21日(金)~5月6日(火・振り替え休日)です。
参加希望の方は、下記までハガキにてお申し込みください。
4月15日(水)必着でおねがいいたします。
【申し込み先】〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会見学会(宮内庁書陵部)
2013年8月更新
■ 日本古文書学会見学会(宮内庁書陵部)のご案内
1. 開催日時
平成25年12月4日(水) 13時~15時(集合時間は12時45分)
2. 見学先
宮内庁書陵部
3. 集合場所
宮内庁書陵部北桔橋門入り口
4. 見学内容
宮内庁書陵部ご所蔵の天平時代古文書、伏見院御文類、織田信長朱印狀、日根野村絵図(コロタイプ)などの貴重史料を見学いたします(予定)。
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会見学会(京都文化博物館)
2013年5月更新
■ 日本古文書学会見学会(京都文化博物館)のご案内
1. 開催日時
平成25年10月14日(月・祝日) 17時~19時(16時45分受付開始)
2. 見学先
京都文化博物館
3. 集合場所
京都文化博物館 2階コネクションホール
4. 見学内容
「陽明文庫の名宝」展を見学致します。
『御堂関白記』、『兵範記』紙背文書(平重盛・頼盛書状)など
『御堂関白記』、『兵範記』紙背文書(平重盛・頼盛書状)など
5. 参加費
500円+展示室入場料
参加ご希望の方は、ハガキに会員・非会員、御所属を明記の上、下記まで申し込みください。10月7日(月)必着でおねがいいたします。
【宛先】〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
2013年度 日本古文書学会大会・総会
2013年5月更新
■ 公開講演
9月21日(土) P.M.1:00から
「和田義盛の乱」について
山本 隆志氏(筑波大学名誉教授)
金沢貞顕書状の編年について
永井 晋氏(神奈川県立歴史博物館専門学芸員)
■ 会場
横浜市中区 関東学院大学KGU関内メディアセンター
(横浜メディア・ビジネスセンター8F)
(横浜メディア・ビジネスセンター8F)
■ 総会
P.M.4:00から
■ 会場
■ 会場
横浜市中区 関東学院大学KGU関内メディアセンター
(横浜メディア・ビジネスセンター8F)
(横浜メディア・ビジネスセンター8F)
■ 懇親会
P.M.6:00から 会費…6,000円(当日受付)
■ 会場
■ 会場
アプローズ(横浜メディア・ビジネスセンター1F)
■ 研究発表
9月22日(日) A.M.9:30より(午前の部)
1、『国家珍宝帳』と「東大寺金堂鎮壇具」の器仗
近藤 好和氏
2、中世西大寺の別当と僧団―所謂「別当乗範置文」の考察を中心に―
村瀬 貴則氏
3、国宝「醍醐寺文書聖教」と「田中穣氏旧蔵典籍古文書」―両史料群が語る中世寺院と権力―
藤井 雅子氏
4、室町期における興福寺大乗院―京都との関係から考える―
土山 祐之氏
5、織田信長と東大寺―『三蔵開封日記』に見る東大寺正倉院開封経緯の検討を中心に―
堺 有 宏氏
P.M.13:00より(午後の部)
6、『桃華蘂葉』を有職故実の書とする定説への疑問
池内 敏彰氏
7、足利義昭政権考 ―有力諸大名による連合政権論の提起―
中川 貴皓氏
8、最上義光再考―古文書の観点から―
松尾 剛次氏
9、「おもろさうし」にみえる干支について活動について
中野 栄夫氏
10、善性寺文書にみる彰義隊屯所問題
伊藤 綾氏
11、「大村家什書」について―大村益次郎宛書翰を中心として―
石田 充敏氏
12、足尾銅山鉱毒事件における請願書・陳情書―明治三五・三六年提出分を中心として―
福井 淳氏
※会員以外の方のご来場も歓迎します。
※会員以外の方は、1日目の公開講演会の入場は無料ですが、2日目の研究発表会は受付で参加費500円をお納めください。
※会員以外の方は、1日目の公開講演会の入場は無料ですが、2日目の研究発表会は受付で参加費500円をお納めください。
※この研究会は終了しました。
■ 文書見学会
9月23日(月) A.M.10:00から (集合場所:金沢文庫1階エントランスホール 集合)
参加費無料
参加費無料
■ 会場
横浜市金沢区 神奈川県立金沢文庫
金沢文庫文書(「金沢貞顕書状」)・称名寺聖教紙背文書(「順忍書状」)などの見学
※見学会は、1日目・2日目の参加の会員に限らせていただきます。
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会見学会(大阪城天守閣)
2012年8月更新
■日本古文書学会見学会(大阪城天守閣)のご案内
■ 場所
大阪城天守閣
■ 日時
11月23日 金曜日(祝日) 14時~16時 (受付は13時45分から)
■ 集合場所
天守閣改札前
■ 参加費
500円
近年の新規収集品を中心として、織豊期~江戸初期の大阪城天守閣収蔵文書を拝見致します。
なお、特別展「秀吉の城」も開催中ですので、あわせてご覧ください。
会期は10月6日(土)~11月25日(日)です。
参加希望の方は、下記までハガキにてお申し込みください。
11月15日(木)必着でおねがいいたします。
なお、特別展「秀吉の城」も開催中ですので、あわせてご覧ください。
会期は10月6日(土)~11月25日(日)です。
参加希望の方は、下記までハガキにてお申し込みください。
11月15日(木)必着でおねがいいたします。
■ 申し込み先
〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
史料見学会(国立歴史民俗博物館・東京大学史料編纂所)
2012年5月更新
■ 国立歴史民俗博物館の見学会のご案内
1. 開催日時
平成25年10月13日(日) 午後1時~午後3時30分(午後12時30分受付開始)
2. 見学先
国立歴史民俗博物館
3. 集合場所
国立歴史民俗博物館 通用口
4. 見学史料
中山法華経寺所蔵日蓮真蹟遺文のうち、観心本尊抄(国宝)、立正安国論(国宝)、法華取要抄(以下重文)、富木殿御返事、寺泊御書、天台肝要文集、秘密要文、三教指帰抄、病御消滅曼荼羅本尊等約20点を、日本古文書学会前会長・立正大学名誉教授中尾堯先生のご解説を伺いながら見学、熟覧致します。
【参考資料】『中山法華経寺史料』(吉川弘文館)、『千葉県の歴史』資料編中世2(県内文書1)
なお詳細については、決まり次第、本学会ホームページで更新致します。
【参考資料】『中山法華経寺史料』(吉川弘文館)、『千葉県の歴史』資料編中世2(県内文書1)
なお詳細については、決まり次第、本学会ホームページで更新致します。
5. 参加費
無料
6. 参加人数
40名前後を予定
※本見学会は、国立歴史民俗博物館と当学会との共催によるものです。
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
2012年度 日本古文書学会大会・総会
2012年4月更新
■ 公開講演
9月22日(土) P.M.1:00から
聖武天皇による政治と救済
森本 公誠氏 (東大寺総合文化センター総長)
信長の安土 ―文書に見る天下人の拠点―
仁木 宏氏 (大阪市立大学大学院文学研究科教授)
■会場:奈良市水門町 東大寺総合文化センター(金鐘ホール)
〒630-8208 奈良市水門町100番地
■ 総会
P.M.4:00から
■会場:奈良市水門町 東大寺総合文化センター
■ 懇親会
P.M.6:00から 会費…6,000円(当日受付)
■会場:奈良国立博物館レストラン 葉風泰夢 (ハーフタイム)
■ 研究発表
9月23日(日) A.M.9:30より(午前の部)
1. 「春日権現験記」詞書生成と集成の場 ―貞慶関係抄物を中心として―
坪内 綾子氏
2. 中世興福寺における「良家」の相承と門跡 ―東院「僧正憲信置文」を中心に―
高山 京子氏
3. 興福寺別当と「三度長者宣」
石附 敏幸氏
4. 近世前期村落における土地売買証文の一書式 ―北武蔵を事例に―
栗原 健一氏
5. 近世後期の内願と幕藩関係 ―熊本細川家の対鑓・先箱願一件を素材として―
山本 英貴氏
P.M.1:00より(午後の部)
6. 中世叙位制度の展開と叙位関連文書
佐古 愛己氏
7. 太政官符案の保管と利用 ―官文殿を中心として―
高橋 邦幸氏
8. 徳大寺家の家人組織と機能
佐伯 智広氏
9. 室町時代後期における東大寺の納所の活動について ―本僧坊供方を中心に―
畠山 聡氏
10. 中世京都における法華宗四条門流の動向
長崎 健吾氏
11. 戦国期毛利氏における「穂田」元清
石畑 匡基氏
12. 足利義昭による「当家再興」
水野 嶺氏
■会場:奈良市水門町 東大寺総合文化センター
※会員以外の方のご来場も歓迎します。
※会員以外の方は、1日目の公開講演会の入場は無料ですが、2日目の研究発表会は受付で参加費500円をお納めください。
※会員以外の方は、1日目の公開講演会の入場は無料ですが、2日目の研究発表会は受付で参加費500円をお納めください。
■ 文書見学会
9月24日(月) A.M.10:00から (集合場所:東大寺総合文化センターロビー)
東大寺文書(「観応二年分文書勘渡帳」「黒田庄悪党交名」「戒壇院牛玉宝印起請文」)などの見学。
※参加費無料。
※見学会は、1日目・2日目の参加の会員に限らせていただきます。
※この大会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
史料見学会(東京大学史料編纂所)
■ 東京大学史料編纂所の見学会
1. 開催日時
平成25年11月11日(月) 午前11時~午後1時(午後10時30分受付開始)
2. 見学先
東京大学史料編纂所
3. 集合場所
東京大学史料編纂所 1階ロビー
4. 見学史料
国宝『島津家文書』や重要文化財『近藤重蔵関係資料』『江戸幕府儒官林家関係資料』のうち対外関係史料のほか、慈鎮和尚夢想記・楽人多家関係文書などの新収史料など、30点ほど。
なお詳細については、決まり次第、本学会ホームページで更新致します。
なお詳細については、決まり次第、本学会ホームページで更新致します。
5. 参加費
無料
6. 参加人数
30名前後を予定
※この見学会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
日本古文書学会研究会
■ 研究会のご案内
■ 関西学院大学
■日 時
2月18日土曜日13時~15時(12時45分受付開始)
■集合場所
関西学院大学(阪急電鉄今津線甲東園または仁川駅下車)
図書館(時計台裏手)入口のエントランスホール
図書館(時計台裏手)入口のエントランスホール
■参 加 費
500円
関西学院大学所蔵の東寺文書、および近世文書(灘の酒造関係等)を見学します。
お問い合わせは、関西学院大学図書館利用サービス課 古文書室担当 羽田真也氏まで。
TEL:0798-54-6123、FAX:0798-51-0911
お問い合わせは、関西学院大学図書館利用サービス課 古文書室担当 羽田真也氏まで。
TEL:0798-54-6123、FAX:0798-51-0911
参加希望者はお名前・連絡先明記の上、下記(京都大学 元木研究室)までハガキで申し込んでください。2月10日必着です。
■京都府立総合資料館
■日 時
3月13日火曜日13時~16時(12時45分受付開始)
■集合場所
京都府立総合資料館(京都市営地下鉄烏丸線・北山駅下車)
総合資料館入口
総合資料館入口
■参 加 費
500円
東寺百合文書を上島有先生のご解説を承りながら見学します。今回は、当時百合文書の料紙見学会の4回シリーズの最後になります。中世文書全体のまとめをしますので、上島先生のご著書『中世日本の紙―アーカイブズ学としての料紙研究―』(日本史史料研究会刊)の、第二章から第六章まで目を通していただくとわかりやすいかと思います。
お問い合わせは下記元木研究室まで。TEL075-753-6681
参加希望者はお名前・連絡先明記の上、下記(京都大学 元木研究室)までハガキで申し込んでください。3月5日必着です。
参加希望者はお名前・連絡先明記の上、下記(京都大学 元木研究室)までハガキで申し込んでください。3月5日必着です。
〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町 京都大学大学院人間・環境学研究科 元木研究室
※2月10日までに申し込まれる方は、どちらの研究会に参加されるか、または双方参加の旨を明記してください。
※2月10日までに申し込まれる方は、どちらの研究会に参加されるか、または双方参加の旨を明記してください。
※この研究会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |
平成23年度(2011年)日本古文書学会学術大会
■ 公開講演
9月24日(土)P.M.1:00 から
東京都渋谷区 國學院大學渋谷キャンパス
〒150-8440 東京都渋谷区東4-10-28
東京都渋谷区 國學院大學渋谷キャンパス
〒150-8440 東京都渋谷区東4-10-28
宗教文書としてみる日蓮真蹟
中尾 堯氏(立正大学名誉教授)
「料紙の変遷表」覚書
湯山 賢一氏(奈良国立博物館館長・本会会長)
■ 研究発表
9月25日(日)A.M.9:30 から
東京都渋谷区 國學院大學渋谷キャンパス
東京都渋谷区 國學院大學渋谷キャンパス
平安期・法隆寺文書二題 ―施鹿院・「伝教院」から法隆寺を見る―
河野 昭昌氏
「東大寺凝然大徳筆聖教類紙背文書」にみる鎌倉時代の戒壇院
山脇 智佳氏
鎌倉後期における恩賞給付システムと鎮西支配 ―蒙古合戦勲功賞を中心に―
池松 直樹氏
中世伊豆国三嶋社と神宮寺 ―「三嶋大社矢田部文書」にみる供僧・社僧の実態を中心に―
吉永 博彰氏
失われた国宝『信貴山縁起絵巻』「山崎長者巻」第一段詞書
―立正大学図書館所蔵模本の意味―
―立正大学図書館所蔵模本の意味―
佐多 芳彦氏
五山禅宗寺院の文書管理と重書案
原田 正俊氏
武家祈祷料所としての植松荘
石田 出氏
戦国期京都における金融について
―天文十五年分一徳政令史料の再検討―
―天文十五年分一徳政令史料の再検討―
酒匂 由紀子氏
奉書形式文書からみた尼子氏の出雲国統治
戸谷 穂高氏
新出の織田信長黒印状の紹介
竹本 千鶴氏
大和家文書について ―散逸した文書とその問題点―
古川 元也氏
『江戸往来』の諸本と「江戸」
石山 秀和氏
デジタル史料画像の検索・閲覧システムについて
―科学研究費基盤研究(S)「史料デジタル収集の体系化に基づく歴史オントロジー構築の研究」の現状―
―科学研究費基盤研究(S)「史料デジタル収集の体系化に基づく歴史オントロジー構築の研究」の現状―
林 譲 氏
会員以外の方のご来場も歓迎します。
※1日目の講演会の入場は無料ですが、2日目の報告会は、会員以外の方は資料代500円をいただきます。
※1日目の講演会の入場は無料ですが、2日目の報告会は、会員以外の方は資料代500円をいただきます。
■文書見学会
9月26日(月)A.M.10:00 ~ 12:00
國學院大學所蔵 八代国治旧蔵文書・森田清太郎旧蔵文書・畠山文書などの見学
※見学会は、1日目・2日目参加の会員に限らせていただきます。
國學院大學所蔵 八代国治旧蔵文書・森田清太郎旧蔵文書・畠山文書などの見学
※見学会は、1日目・2日目参加の会員に限らせていただきます。
※この大会は終了しました。
| ページの先頭に戻る |